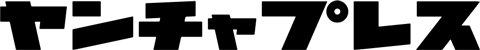愛するペットを失う悲しみは、言葉では言い尽くせないものがあります。その喪失感を埋める手段として、近年、海外の一部セレブの間で「ペットのクローン」を作成する動きが注目を集めています。しかし、その華やかな話題の裏側には、動物たちの健康リスクや倫理的な矛盾、そして見過ごされがちな犠牲が存在します。私たち飼い主が知っておくべきクローン技術の「光と影」について、冷静に考えたいと思います。

まるでSFの世界? セレブたちがすがる「復活」の技術
愛するペットとの別れは、飼い主にとって身を引き裂かれるような体験です。「もう一度会いたい」「できることなら生き返らせたい」と願う気持ちは、決して特別なものではありません。かつてはSF映画の話だった「死んだペットの復活」が、今や一部の富裕層の間で現実の選択肢となりつつあります。
最近では、アルゼンチンのハビエル・ミレイ大統領が、亡くなった愛犬イングリッシュ・マスティフ「コナン」の遺伝子を用いて複数のクローン犬を作成したことが大きな話題となりました。彼はそのクローン犬たちを「4本足の子どもたち」と呼び、強い愛情を注いでいると報じられています。
また、歌手のバーブラ・ストライサンドが、亡き愛犬「サマンサ」の細胞から2匹のクローン犬を誕生させた事例もよく知られています。さらに、元NFLスター選手のトム・ブレイディがこの技術に関心を示しているとの報道もあり、ペットクローンは一部で「究極のペットロス対策」として語られるようになりました。
数百万円から数千万円という高額な費用を支払えば、愛犬と同じ遺伝子を持つ個体を迎えられる時代。しかし、この技術を無条件に「夢の技術」と捉えてよいのでしょうか。筆者は、その背後にある科学的限界と動物福祉の観点から、看過できない構造的問題に目を向ける必要があると考えます。
科学が教える現実 ──「コピー」は「オリジナル」ではない
まず、ペットクローン技術の実態を正しく理解することが重要です。現在主流となっているのは、「体細胞核移植(SCNT)」と呼ばれる手法です。これは、1996年に世界初のクローン羊「ドリー」を生み出した技術と基本的に同じものです。
その工程は、ドナーとなるペットの体細胞から核を取り出し、核を除去した別のメス犬の未受精卵に移植します。細胞分裂を始めた胚を代理母犬の子宮に移植し、妊娠・出産に至るという流れです。
こうして誕生した個体は、遺伝子配列の上では元のペットとほぼ同一です。しかし、「遺伝子が同じ=同じ犬」ではないという科学的事実です。
こうして生まれた子犬は、元のペットと「遺伝的には」ほぼ同一です。しかし、ここで強調しなければならないのは、「遺伝子が同じ=同じ犬」ではないという科学的事実です。
生物の容姿や性格は、DNAだけで決まるものではありません。毛の模様ひとつをとっても、胎内環境や成長過程の偶然によって変化します。実際に、クローン猫は、オリジナルとは異なる毛色を持っていました。
さらに、重要なのが「性格」です。生まれ持った気質に加え、育った環境、飼い主との関係性や経験といった後天的要因が大きく影響します。バーブラ・ストライサンド自身も、クローン犬たちが「サマンサとは違う性格を持っている」と語っています。
「あの子が戻ってくる」と期待してクローンを迎えても、そこにいるのは外見が似ている可能性のある、別の個体なのです。
成功率の低さと、語られない「失敗」のリスク
ペットクローン技術の大きな課題のひとつが、その成功率の低さです。技術は進歩しているものの、SCNTによるクローン作成は依然として効率的とはいえません。
専門的な論考によれば、1匹の健康なクローン犬を誕生させるためには、多くの失敗が必要となります。多くの胚は着床しなかったり、妊娠初期に流産したりします。あるいは妊娠が進んでも死産となるケースや、生後間もなく亡くなってしまうケースも少なくありません。
さらに、生まれたクローン動物には特有の健康リスクが伴います。よく知られている「過大子症候群(Large Offspring Syndrome)」をはじめ、免疫不全、骨格異常、臓器障害などの健康リスクが指摘されています。
クローン羊ドリーが比較的若い年齢で関節炎や肺疾患を発症し、安楽死となった事実は象徴的です。犬において同様のリスクが完全に否定されているわけではなく、クローン個体が生涯にわたり健康問題を抱える可能性は、飼い主が理解しておくべき現実です。
「見えない犠牲者」──ドナー犬と代理母犬
筆者が特に懸念を抱くのは、クローン作成の過程で利用されるドナー犬と代理母犬の存在です。
1匹のクローンを作るためには、単に「元の犬の細胞」があればよいわけではありません。まず、核を受け入れるための「卵子」が必要です。これを提供するのは、ドナーとなるメス犬です。卵子を採取するためには、排卵誘発剤などのホルモン投与や、開腹手術など科的処置が伴う場合があります。
次に、受精卵(胚)を育てて出産するための「代理母犬」が必要です。代理母犬には妊娠・出産の身体的負担が繰り返し課されます。成功率が低いがゆえに、複数の代理母犬に同時に胚移植が行われるケースもあります。報告によれば、1匹のクローン犬を誕生させるために、数十個の胚が作られ、複数の代理母犬が妊娠を強いられるケースもあるといいます。
これらのドナー犬や代理母犬たちは、研究施設や企業の管理下で飼育されています。彼女たちは、誰かの「愛犬」を再生させるための「製造装置」として扱われてはいないでしょうか。ホルモン剤の投与、繰り返される採卵や胚移植の手術、妊娠・出産のなどは、動物福祉の観点から慎重に検討されるべき問題です。
「自分の愛犬にもう一度会いたい」という飼い主の純粋なエゴの裏側で、名前も知られない数多くの犬たちが、不必要な医療処置と身体的負担を強いられているを受けている。英国王立動物虐待防止協会(RSPCA)などが、ペットクローンに対して強い懸念を示している背景には、こうした事情があります。
商品化される「命」と倫理的な問い
世界には今も、多くの犬や猫が保護施設で新しい家族を待っています。その一方で、特定の個体を再生するために多額の資金が投じられ、さらにその過程で別の犬たちが犠牲になっているという現実があります。これは、命の「商品化」や「格差」を象徴しているようにも映ります。
ミレイ大統領のように、クローン技術を「家族の再生」と捉える価値観を、個人の自由として一概に否定することは難しいかもしれません。ペットロスによる絶望は、それほどまでに深いものだからです。しかし、私たちは自問する必要があります。
「愛する犬への愛情」とは、その遺伝子を保存することなのでしょうか? それとも、その子と過ごした唯一無二の時間、紡いだ絆、そしてその命がひとつ限りであるという「尊厳」を大切にすることなのでしょうか。
クローン犬は、亡くなった犬の記憶を持ちません。、亡くなった犬との絆を覚えているのは、飼い主だけです。新しい命(クローン)に、亡くなった犬の面影や役割を過度に押し付けることは、新しく生まれた犬の「個としての尊厳」を無視することにもなりかねません。それは、その子を「その子自身」として愛するのではなく、「身代わり」として愛することになってしまうからです。
命の尊厳と、真の「供養」とは
科学技術の進歩は、私たちに多くの恩恵をもたらしてきました。獣医療の発展により、かつては助からなかった命が救われるようになったことは素晴らしいことです。
しかし、実現可能であることと、倫理的に許容されることは同義ではありません。現状のペットクローン技術には、動物福祉、健康リスク、そして生命倫理の面で、なお多くの課題が残されています。
愛するペットを失った悲しみは、その存在がかけがえのない唯一無二だった証です。その思い出を胸に刻み、もし新たな縁があれば、新たな犬を家族として迎え入れ、新たな関係を一から築いていく。それこそが、動物を愛する私たちが選ぶべき、より健全で未来志向な選択ではないでしょうか。
亡くなったペットが私たちに残してくれたのは、遺伝子情報ではなく、温かく幸せな時間と無償の愛だったはずです。その記憶こそが、私たちのなかで生き続ける「本当の継承」なのです。
The post 愛犬のクローンは本当に「愛」なのか? セレブが選ぶペット再生技術と科学が突きつける不都合な真実 first appeared on ペトハピ.
元の投稿: 犬や猫とハッピーに暮らすための情報と最新ペットニュース - ペトハピ [Pet×Happy]
愛犬のクローンは本当に「愛」なのか? セレブが選ぶペット再生技術と科学が突きつける不都合な真実